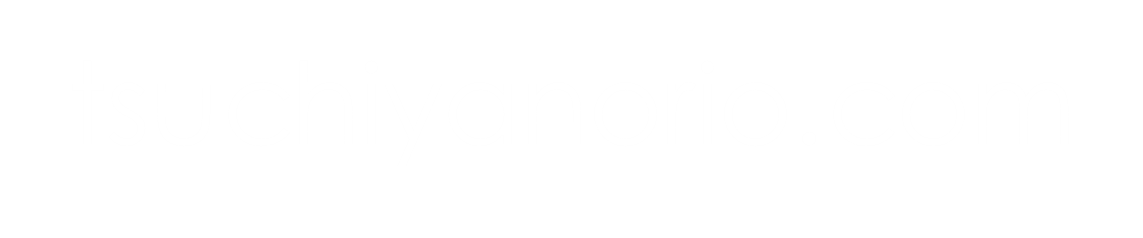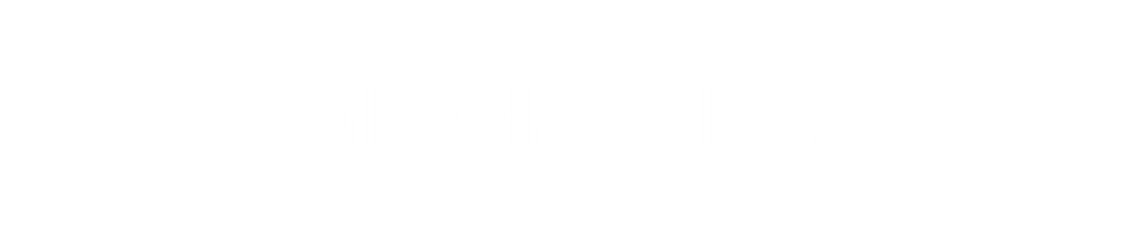M&Aを行うときには、売却価格や従業員の処遇といった条件面だけでなく、どんな手法を使うかを決めることも大切です。手法ごとに特徴やメリット・デメリットを理解した上で、ご自身の目的に応じてベストな選択を行うのが成功の秘訣です。 中小企業のM&Aで用いられる主要な手法について、メリットやデメリットを解説するので、ぜひM&A手法選びの参考にしてみてください。
株式譲渡

株式譲渡は、会社が発行している株式を売買することで、会社の経営権を売り手から買い手に移すM&A手法です。
株式の売買だけで経営権を移転できるのは、株式会社が株式(議決権)の保有割合が多い人の意見ほど反映されやすい仕組みとなっているからです。たとえば全議決権株式のうち3分の2以上を持っていれば、資本金の減資や株式の併合といった会社にとって重要な経営判断を独力で行えます。
この仕組みがあるために、すべての議決権株式を売買することで、実質的に会社の経営権を移すことが可能なのです。
メリット
なんと言っても、カンタンな手続きのみでM&Aを行える点がこの手法の魅力です。
株式に譲渡制限がついている一般的な中小企業を想定すると、「契約の締結」、「譲渡承認の請求」、「株主名簿の書き換え」という3つの手続きのみでM&Aを実施できます。
後述する手法とは異なり、株主総会による特別決議や債権者保護手続きといった面倒なことはしなくて良いので、比較的少ない労力・時間でM&Aを終わらせることができるでしょう。
デメリット
はっきり言うと、売り手にとってデメリットは無いに等しいです。強いて言うならば、会社ごと売却するため、経営者としての地位を失う点や、一部の事業のみを存続させることができない点がデメリットでしょう。
一方で買い手にとっては、簿外債務や自社にとって不必要な資産を引き継ぐリスクがデメリットとなります。株式譲渡では、株式の買収により経営権ごと獲得するため、個別に引き継ぐ資産や権利、負債等を選ぶことができません。そのため、帳簿上に記載されていない債務(訴訟のリスクや回収可能性が低い売掛債権など)や、自社に利益をもたらさない資産を引き継ぐリスクが高いです。
どのようなケースに向いているか
経営権ごと移転する手法であるため、会社売却を目的としたM&Aに最適です。一方で、一部の事業のみを売却することはできないので、本業への集中や不採算事業の整理を目的とした事業売却には使えません。
また、手続きが簡便であるため、中小企業のM&Aにも適しています。実際に中小企業庁が公開しているデータによると、中小企業によるM&Aのうち、40.8%が株式譲渡によって行われたとのことです。M&A手法の中でも特に有名な合併が15%であることを踏まえると、株式譲渡は中小企業にとって馴染みのある手法であると言えます
参考記事:3 M&A実施企業の実態 中小企業庁
事業譲渡

事業譲渡は、売り手が持っている事業の一部もしくはすべてを買い手に移すM&Aの手法です。たとえばA事業を譲渡する際には、A事業で使っている資産や負債、知的財産等を移転することになります。
メリット
事業譲渡では、1つ1つの事業(資産等)ごとに売買するかどうかを決めます。そのため、売り手は売却したい事業のみを売却できますし、買い手は欲しい部分だけ買収できます。
この仕組みがあるため、売り手企業は不採算事業を売却し、そこで得られた現金を本業に投入することが可能です。また、会社を経営する権利を手元に残せるので、引き続き残った事業で会社を持続・成長させることができます。
一方で買い手側は、欲しいものだけを買収することで、簿外債務や必要ない資産等を引き継がずに済みます。一部のみを買収するので、会社ごと買収する株式譲渡と比べると買収金額も少なく済むのが一般的です。
デメリット
事業譲渡で一番のデメリットになるのが、手続きの面倒くささです。買収する資産や権利ごとに契約を結び直す必要があるので、負担は株式譲渡よりも圧倒的に増加します。
一方で売り手の視点に立つと、競業避止義務が規定されるリスクの高さが大きなデメリットとなるでしょう。競業避止義務とは、「同一市町村とその隣接する市町村の中で、売却した事業と同じビジネスを一定期間のあいだ行ってはならない」という義務です。
会社法第21条では、事業譲渡を行った日から20年間にわたって競業避止義務を負うことを原則としています。契約書などで別段の定めがない限り、M&A後の事業展開に支障をきたす恐れがあるので注意した方が良いでしょう。
参考記事:会社法第21条 e-Gov
どのようなケースに向いているか
この手法は、売り手と買い手ともに一部の事業だけを売買したい時に向いています。
たとえば「本業が忙しくて他の事業に集中できない」という場合、本業以外を売却すれば、本業にすべてのリソースを集中させることができます。また、売却した資金を使って、より一層本業の成長を加速できるかもしれません。
また個人事業主によるM&Aでは、株式を発行していない都合上、株式譲渡の手法が活用できません。したがって、個人事業主が事業すべてを売却する際には、基本的に事業譲渡の手法を用いることになります。
その他

実は、中小企業のM&Aで用いられる手法のうち、ほとんどは「株式譲渡」と「事業譲渡」です。先ほど取り上げた中小企業庁のデータでも、株式譲渡と事業譲渡だけで全体の8割を占めていることからも明らかでしょう。
ただし、まれに株式譲渡や事業譲渡以外の手法でM&Aが行われるケースもあります。その他のM&A手法をカンタンにご紹介するので、頭の片隅にでも入れておくと良いかもしれません。
合併
合併とは、2つ以上の会社が1つの会社に合わさるM&Aの手法です。売り手側の法人格は完全に消滅するので、上記2つの手法と比べると、より従業員同士の結束を強められる可能性があります。
ただし、特別決議や債権者保護などの手続きが原則必要となるため、他のM&A手法と比べると時間や労力を圧倒的に要します。
会社分割
会社分割とは、会社が事業について持っている権利の一部またはすべてを切り離して、それを他の会社が引き継ぐM&Aの手法です。
事業に関する権利をまとめて引き継げるため、事業譲渡のように個別に1つずつ契約し直す必要がありません。ただし、債権者保護手続きが原則不可欠なので、合併と同様に比較的手続きに手間や時間を要します。
参考資料:(参考資料1)中小 M&A の主な手法と特徴 【本文11ページ以下】 経済産業省
まとめ
中小企業のほとんどは、M&Aにおいて株式譲渡または事業譲渡のいずれかの手法を用います。したがって、まずは上記2つの手法について理解し、どちらが自社のM&Aに適しているかを判断するのが最優先となります。
M&Aの手法について、より詳しく知りたい方は下記のサイトもご参照ください。
参考: M&Aの種類とは?分け方や各種類の特徴を徹底解説! M&Aポート
また、M&Aの仲介会社に問い合わせをすれば、無料で詳しくレクチャーを受けることができます。