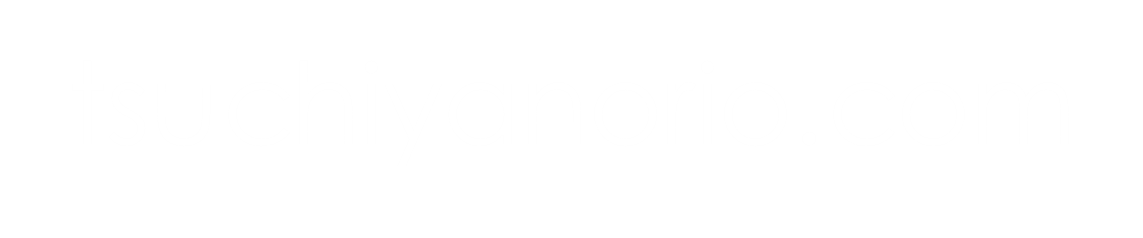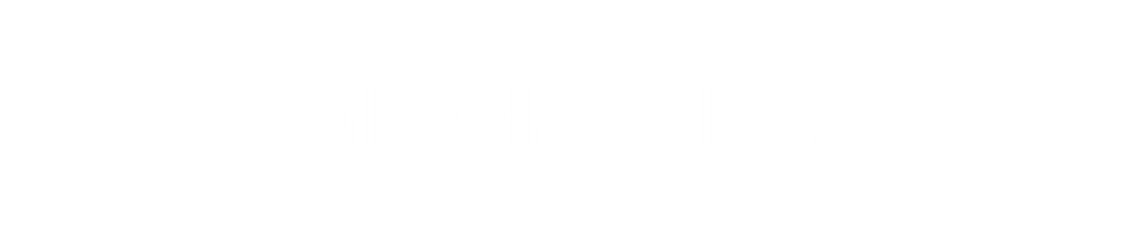会社売却を実施するにあたっては、売却価格の相場を知っておくのが好ましいです。
売却相場を把握しておけば、あらかじめ大体どのくらいで売却できるかを知ることができ、M&Aを実施すべきかどうかの判断を下しやすくなります。
今回の記事では、一般的な中小企業による会社売却の相場をご紹介します。
中小企業だと「時価純資産 + 営業利益の3〜5年分」が相場
中小企業のM&Aでは、時価換算した純資産に3〜5年分の営業利益を足した金額を売却価格とするケースが多いです。
- 売却価格(相場) = 時価純資産 + (営業利益 × 3〜5)
例えば時価純資産が2,000万円、営業利益が400万円、営業利益の3年分を基準にする場合、売却価格は以下のとおり求められます。
- 売却価格 = 2,000万円 + (400万円 × 3) = 3,200万円
会社売却を検討する際は、まずは上記の計算式に当てはめて、大体どのくらいの金額で売却できそうかを算定しておきましょう。
事業売却と会社売却でも相場は大きく変わる
実は、事業売却と会社売却を比べた場合、相場は大きく変わってきます。
この章では、事業売却と会社売却で相場が大きく異なる理由をご紹介します。
事業売却と会社売却の違い
事業売却と会社売却の違いは、売却する対象や範囲にあります。
事業売却は、会社の中にある一部の事業を売却する行為です。
あくまで移動するのは事業用の資産や事業に携わる人員などであり、株式(≒経営権)や関係のない事業の移転は伴いません。
一方で会社売却とは、会社丸ごと売却する行為です。
そのため、株式を含むすべての資産が売り手から買い手に移転します。
事業売却よりも会社売却の方が相場が高くなる理由
一般的には、事業売却よりも会社売却の方が相場は高くなります。
その理由は、会社売却の方が売却する範囲が広いからです。
会社売却では、事業の全てはもちろん、人材やノウハウ、経営権などの目に見えない無形資産もすべて引き継ぎの対象となります。
そのため、一部の資産や権利のみを譲渡する事業売却よりも、相場は大幅に高くなるのです。
なるべく多くの利益を獲得したいならば、会社売却の方法でM&Aを行うようにしましょう。
会社売却では「企業価値」をベースに売買価格を決定する
会社売却の実務では、「企業価値」をベースに最終的な売買価格を決定します。
企業価値の求め方は多岐にわたるため、用いる方法次第では前述した相場とは大きく異なる金額となるケースもあります。
この章では、企業価値の意味や企業価値の求め方をご紹介します。
企業価値とは
企業価値とは、会社の価値を金銭的に表したものです。要するに、「この会社はこのくらいの値段に相当する価値を持ちます」ということを数字で表しているわけです。
会社売却の際には、最終的に売主と買主の交渉次第で価格が決まります。
ですがお互いに希望を言い合うだけでは、お互いにとって納得でき、かつ不利益を被らない価格を決めるのは難しいです。
そこで役に立つのが企業価値です。
次の項でご紹介しますが、企業価値は対象会社の収益性や純資産、他の会社・事例などを参考に算出します。
そのため、企業価値をベースに交渉を進めれば、話し合いがスムーズに進行し、納得できる金額に決まりやすくなります。
企業価値の求め方
企業価値の求め方は、大きく「コストアプローチ」、「インカムアプローチ」、「マーケットアプローチ」の3種類に大別されます。
それぞれ長所と短所は異なるため、企業の性質に応じて最適なアプローチを使い分ける必要があります。
この項では、3種類のアプローチそれぞれについて、特にメジャーな手法をご紹介します。
時価純資産法
時価純資産法とは、資産と負債を一度時価換算し、その上で算出した時価純資産を企業価値とする方法です。
貸借対照表さえ揃えれば、簡単に企業価値を計算できる点が利点です。
また、会計上のルールに則って作られた貸借対照表を用いるため、客観性の高い企業価値を求められます。
ただし、将来的な収益性を加味していないため、成長性の高いベンチャー企業などには適していません。
とはいえ計算の簡便さや客観性の高さから、中小企業によるスモールM&Aでは広く用いられています。
一般的な中小企業であれば、時価純資産法を用いて、そこに営業利益の3〜5年分を足した金額を相場として考えても問題ないでしょう。
なお時価換算とは、貸借対照表に記載されている資産や負債を、その時点における正確な価値に直すことです。例えば売掛金から回収不能額を引くことが、時価換算に該当します。
純資産を時価換算することで、より客観性や合理性の高い企業価値を求められるわけです。
DCF法
DCF法とは、評価対象の企業が将来にわたって得られるフリーキャッシュフロー(FCF)の現在価値を基準に、企業価値を求める方法です。
収益性や無形資産の価値、シナジー効果などを最大限考慮できるため、あらゆるM&Aにおいて活用できる手法です。
ただし、事業計画書の数字をベースにFCFを求めるため、売主の恣意性や主観が入りやすいのが難点です。
また、計算には高度な専門知識を要するため、外部のM&Aアドバイザーに算出してもらうのがおすすめです。
類似会社比較法
類似会社比較法とは、事業内容などが類似している上場企業の株価指標を基準に、企業価値を求める方法です。
マルチプル法とも呼ばれるこの方法では、類似企業の「EBITDA倍率」や「PER」、「PBR」などの指標を活用します。
事業内容が類似する企業を基準とするため、客観性の高い企業価値を求められます。
ただし、ニッチな事業などで比較対象が存在しない場合には、類似会社比較法は活用できません。
客観性が高い上に計算も容易であるものの、使用できるかどうかはケースバイケースなので注意しましょう。
まとめ
会社売却の相場は、時価純資産と営業利益を把握していれば、簡単に求めることができます。
ただし、成長性が高いベンチャー企業などの場合は、今回お伝えした相場が当てはまりにくいといえます。
より正確に売却できそうな金額を知りたい方は、ぜひM&Aポートにご相談ください。