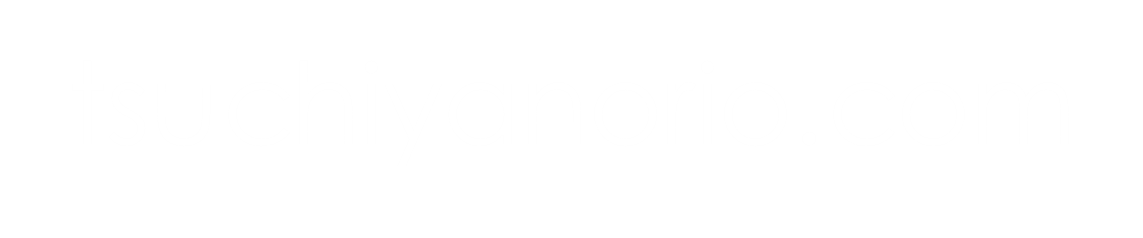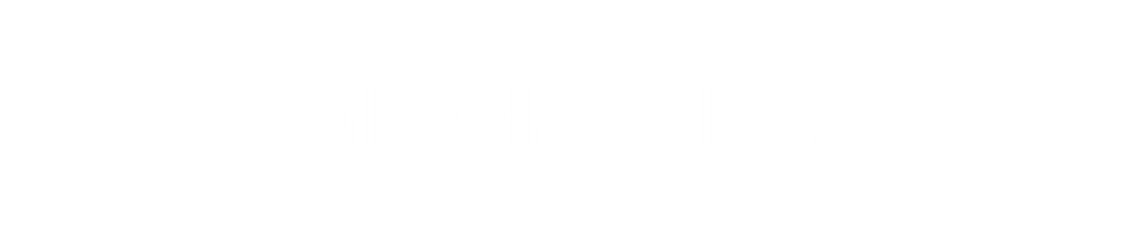M&Aといえば、難しくて複雑なイメージを持たれやすいです。
しかし実は、手順自体は単純であり、流れを把握すればスムーズにM&Aを行えます。
この記事では、M&Aの一般的な手順を6つに分けて順番にご紹介します。
手順①:M&Aに向けて検討・準備を進める
まずは、M&Aの検討や準備として3つやるべきことがあります。
1つ目は、M&Aを行う目的を明らかにすることです。
そもそもM&Aは、既存事業の拡大や事業承継など、何かしらの目的を達成する手段に過ぎません。
目的もなくM&Aを行っても、費用や時間を無駄にするだけで、効果を実感できません。
M&Aによる恩恵を受けるためにも、まずはどのような目的でM&Aを行うかを明らかにしましょう。
2つ目は、M&Aアドバイザー(仲介会社)の選定です。
M&Aの業務を遂行するには、幅広い専門知識やリソース、ネットワーク(人脈)が必要です。
経営者と社員のみでM&Aを行うと、相手探しに難航したり、契約や交渉でトラブルに発展する恐れがあります。
そうならないためにも、信頼できるM&Aアドバイザーからサポートを受けることが重要なのです。
M&Aアドバイザーの業務を行う会社は、金融機関や士業事務所など多岐に渡ります。
中小企業のM&Aであれば、相手探しから契約締結までを一貫してサポートしてくれる仲介会社に依頼するのがオススメです。
M&Aアドバイザーがしてくれるサポートの内容や依頼費用に関しては、以下の記事が参考になります。
手順②:M&Aの交渉相手を探す
次の手順では、M&Aの交渉相手を探します。
基本的には、契約を締結したM&Aアドバイザー(仲介会社)が交渉相手を探すサポートを担います。
交渉相手を探す際には、本格的な提案資料とは別に、「ノンネームシート」と呼ばれる資料を作成します。
ノンネームシートとは、自社の具体的な情報が漏洩しない範囲で、M&Aの提案を行える資料です。
交渉相手を探す際には、まずノンネームシートを相手方に提示し、興味を持ってくれた相手と秘密保持契約を締結した上で、具体的な提案資料を渡します。
この手順を踏むことで、売り手企業の機密情報やM&Aを行う旨が取引先などに漏洩するリスクを軽減できるわけです。
手順③:交渉を行い、基本合意書を締結する
提案資料を確認し、買い手側が本格的にM&Aの交渉を進めたいとなったら、まずは売り手と買い手の経営者同士でトップ面談を行います。
トップ面談では、互いの経営者が顔を合わせて、経営理念や価値観などを共有します。
考え方の面でお互いの理解が深まったら、いよいよ本格的に条件面の交渉を始めます。
具体的に交渉すべき項目は、主に次のとおりです。
- 売買金額
- 用いるM&Aの手法(株式譲渡や事業譲渡など)
- M&Aのスケジュール
- 従業員および役員の処遇
売り手と買い手の間で条件面で合意できたら、合意内容を「基本合意書」と呼ばれる書面に残します。
基本合意書を作成すれば、合意内容を明らかにして、お互いの認識が相違する事態を防ぐことができます。
なお基本合意書には、買い手の意向で「独占交渉権」が付与されることがあります。
独占交渉権が付与されると、売り手側は他の買い手候補とは一切交渉できなくなるので注意が必要です。
手順④:デューデリジェンスを行う
基本合意書の締結を終えたら、デューデリジェンスを実施します。
デューデリジェンスとは、簡単にいうと売り手企業を法務や会計、税務などあらゆる視点からくわしく調査するプロセスです。
デューデリジェンスを行うことで、買い手側は売り手企業が抱える潜在的なリスクを明らかにできます。
あらかじめリスクを把握することで、実態に見合わない金額で買収したり、買収後に思わぬ損失を負うリスクを減らせます。
後々になって訴訟に発展する恐れもあるため、売り手側は自社にとって都合が悪い情報でも包み隠さずに開示する必要があります。
手順⑤:最終的な交渉・契約を行う
デューデリジェンスの結果を踏まえて、買い手側は買収価格の修正やM&Aを行って問題ないかの最終判断を行います。
買い手がM&Aを実行する旨を決断したら、売り手と買い手の間で最終的な条件面の交渉を行います。
この交渉で双方がM&Aを実施することで合意したら、最終的な契約を締結します。
最終的な契約書の内容は、用いるM&Aの手法によって異なります。たとえば株式譲渡ならば「株式譲渡契約書」、事業譲渡ならば「事業譲渡契約書」となります。
手法によって細かい部分は変わってきますが、最終的な契約書には主に以下の項目を盛り込みます。
- M&Aの基本条件(売買価格や、社員・役員の処遇など)
- 表明保証(相手に伝えた情報や契約書に記載された内容が事実である旨を証明する)
- 前提条件(契約条件を満たさない場合に、代金の支払いや資産の譲渡をおこなわない旨を定める)
- 遵守事項(代金支払いまでに重要な資産を売却しない旨や、経営に直結する意思決定を遂行しない旨を約束する)
- 補償条項(契約内容に違反したときの補償を定める)
- 解除条項(重要な契約違反が生じた時に、契約を解除できる旨を定める)
契約書に関してくわしく知りたい方は、下記の記事を参照してみてください。
手順⑥:クロージングを実行する
契約を締結しても、M&Aの手順はすべて終わったわけではありません。
対価の支払いや各種資産・権利等の移転を終えて、ようやくM&Aの手順はすべて完了となります。
よって、契約を締結させた後は、買い手から売り手への対価の支払いと、売り手から買い手への各種資産・権利等の移転を行う必要があります。
M&Aではこの手続きを、「クロージング」と呼びます。
合併などによる大規模なM&Aでは、契約締結からクロージングまでに数ヶ月に及ぶ期間が生じる傾向があります。
一方で株式譲渡による小規模なM&Aでは、契約締結と同日中〜翌日中にクロージングを済ませる傾向があります。
クロージングの具体的な手続きに関しては、以下の記事が参考になります。
まとめ
M&Aの手順をまとめると以下のとおりです。
- M&Aに向けた検討・準備
- M&Aの交渉相手探し
- 交渉の実施・基本合意書の締結
- デューデリジェンスの実施
- 最終的な交渉・契約締結
- クロージングの実行
今回お伝えしたように、M&Aの手順自体は決して複雑ではありません。
実際にM&Aを行うときには、ぜひ今回ご紹介した手順を参考にしてみてください。
M&Aについてさらに詳しく知りたい方は、下記のサイトを参考にしていただければと思います。